Vol.01 ゼロトラスト時代のセキュリティ〜基本概念と設計思想〜
- atsu wada
- 2025年4月25日
- 読了時間: 14分
更新日:2025年9月16日

この記事であなたがやるべきこと
後述する「ゼロトラストの中核となる5つの設計原則」を理解して、
従来の境界型セキュリティとの違いを把握し、
自社のセキュリティ体制をゼロトラストモデルへ移行するための第一歩を踏み出せるようになること
はじめに

「社内ネットワークだから安全だろう」
「VPNを導入しているから外部からのアクセスは守られている」
このような考え方で、あなたの組織のセキュリティは本当に守られているでしょうか?
近年、クラウドサービスの普及やリモートワークの一般化、そしてサイバー攻撃の高度化により、従来の境界型セキュリティモデルでは十分な防御ができなくなっています。これまでは「内部は信頼し、外部からの脅威を防ぐ」という考え方が主流でしたが、もはやそれだけでは不十分な時代になりました。
そこで注目を集めているのが「ゼロトラスト」という新しいセキュリティの考え方です。「信頼せず、常に検証する」を基本原則とするこのアプローチは、現代のIT環境に適したセキュリティモデルとして多くの組織に採用されつつあります。
本記事では、ゼロトラストの基本概念と設計思想について解説し、なぜ今この考え方が重要なのか、そして組織のセキュリティ体制をどのように変革していくべきかについて説明します。
従来の境界型セキュリティモデルの限界

まずは、従来のセキュリティモデルとその限界について理解しましょう。
境界型セキュリティとは?
境界型セキュリティ(ペリメターセキュリティ)は、組織のネットワークを「内側」と「外側」に分け、境界に防御を集中させるモデルです。
このモデルは「城壁と堀」に例えられます
城壁(ファイアウォール)で外敵の侵入を防ぐ
堀(DMZ)で緩衝地帯を設ける
城内(内部ネットワーク)は基本的に安全とみなす
具体的な実装としては、以下のような対策が一般的でした
境界ファイアウォールの設置
VPN(仮想プライベートネットワーク)の利用
IDS/IPS(侵入検知・防止システム)の導入
メールゲートウェイでのウイルスチェック
境界型モデルの問題点
このモデルには、現代のIT環境において以下のような深刻な問題があります
内部脅威への対応の弱さ
いったん内部に侵入されると、ほぼ無防備な状態になります(横方向の移動が容易)
クラウド環境との相性の悪さ
SaaS、IaaS、PaaSなどのクラウドサービスの利用で「境界」が曖昧になっています
リモートワークの一般化
従業員が様々な場所から様々なデバイスでアクセスする状況に対応できません
高度化するサイバー攻撃
標的型攻撃やサプライチェーン攻撃など、境界を突破する手法が次々と登場しています
実例:境界型セキュリティの限界を示す事例
ケース1:内部者による情報漏洩
ある企業では、元従業員が退職前に社内ネットワークから顧客情報をダウンロードし、競合他社に持ち出すという事件が発生しました。内部ネットワークへのアクセス権を持つ従業員は、ほぼ制限なく社内リソースを閲覧できる状態だったため、このような情報流出を防ぐことができませんでした。
ケース2:VPNの脆弱性を突いた侵入
別の企業では、リモートアクセス用のVPNサーバーの脆弱性が攻撃者に悪用され、内部ネットワークに侵入されました。攻撃者は一度侵入した後、数か月にわたって内部ネットワーク内で検出されることなく活動し、機密データを窃取していました。境界を突破されると内部での監視が不十分だったのです。
これらの事例は、内部を「信頼できる領域」とみなす従来のモデルが、もはや現代のビジネス環境には適していないことを示しています。
ゼロトラストセキュリティとは何か?

ゼロトラストの基本的な考え方
ゼロトラストセキュリティとは、「何も信頼せず、常に検証する」という考え方に基づくセキュリティモデルです。
ゼロトラストの核心
"Never Trust, Always Verify"(決して信頼せず、常に検証する)
内部と外部の区別なく、すべてのアクセスを検証する
最小権限の原則を徹底する
継続的な監視と検証を行う
ゼロトラストでは、以下の前提に立ちます
ネットワークは常に敵対的環境とみなす
内部・外部の脅威は常に存在する
ネットワークの場所だけでは十分な信頼の基準にならない
すべてのデバイス、ユーザー、ネットワークトラフィックは検証対象
従来モデルとゼロトラストの違い
従来のモデルとゼロトラストモデルの違いを表にまとめると以下になります。
項目 | 従来の境界型モデル | ゼロトラストモデル |
|---|---|---|
信頼の基準 | ネットワークの場所(内部か外部か) | ID、デバイス、コンテキスト、振る舞い |
アクセス制御 | 一度認証すれば広範囲のアクセスが可能 | 常に最小権限のみを付与 |
監視の焦点 | 境界での侵入検知 | すべてのトラフィックとエンドポイントの継続的監視 |
保護の対象 | ネットワーク境界 | データとアイデンティティ |
認証 | 単一要素認証が一般的 | 多要素認証と継続的な再検証 |
ゼロトラストの歴史と発展
ゼロトラストという概念は、2010年にForrester Researchのアナリスト、ジョン・キンダーヴァッグによって提唱されました。当初は「ネットワークの信頼ゾーンを排除する」という考え方から始まりましたが、その後の技術の発展と共に以下のように進化しています:
2010年代前半
ゼロトラストの概念が提唱される
セグメンテーションとマイクロペリメータの考え方が発展
2010年代後半
Googleの「BeyondCorp」モデルが公開される
クラウドサービスの普及によりアイデンティティ中心の考え方が強まる
2020年代
COVID-19パンデミックによるリモートワークの加速
NIST(米国国立標準技術研究所)がゼロトラストアーキテクチャのガイドラインを公開
サプライチェーン攻撃の増加によりゼロトラストの重要性が高まる
ゼロトラストの中核となる5つの設計原則

ゼロトラストセキュリティを実現するためには、以下の5つの重要な設計原則を理解し、実装することが必要です。
1. 最小権限の原則
原則の内容
必要最小限の権限だけを、必要な時に、必要な期間だけ付与する
実装のポイント
ロールベースのアクセス制御(RBAC)の導入
ジャストインタイムアクセス(JIT)の実現
特権アクセス管理(PAM)の強化
定期的な権限の棚卸しと見直し
実践例
データベース管理者が本番データベースにアクセスする際、作業チケットに基づいて一時的に権限を付与し、作業完了後に自動的に権限を失効させる仕組み。
2. 常時検証の原則
原則の内容
すべてのアクセスを継続的に検証し、一度認証しただけで信頼しない
実装のポイント
多要素認証(MFA)の義務付け
継続的な認証(Continuous Authentication)
リスクベース認証(動的な認証強度の調整)
セッションの定期的な再検証
実践例
ユーザーが機密データにアクセスする際、初回ログインだけでなく、一定時間ごとや行動パターンに異常があった場合に再認証を要求する仕組み。
3. アイデンティティ中心のセキュリティ
原則の内容
ネットワークの場所ではなく、アイデンティティを信頼の基盤とする
実装のポイント
強力なアイデンティティ管理基盤の構築
シングルサインオン(SSO)の導入
ID管理とアクセス管理の統合(IAM)
デバイス認証とユーザー認証の組み合わせ
実践例
社内システムへのアクセスを、VPNや社内ネットワークの有無に関わらず、ユーザーIDとデバイスの健全性、振る舞いに基づいて制御する仕組み。
4. 包括的な可視性と監視
原則の内容
すべてのリソース、トラフィック、アクセスを監視し、異常を検知する
実装のポイント
エンドポイントの可視化と監視強化
ネットワークトラフィックの完全な可視化
SIEM(Security Information and Event Management)の導入
ユーザー行動分析(UBA/UEBA)の実施
実践例
ユーザーの通常の行動パターンを機械学習で学習し、勤務時間外の大量ファイルダウンロードなど、異常な行動を自動検出してアラートを発する仕組み。
5. セグメンテーションの強化
原則の内容
システムやネットワークをより小さな単位に分割し、それぞれの間のアクセス制御を細かく実施する
実装のポイント
マイクロセグメンテーションの導入
ソフトウェア定義境界(SDP)の活用
アプリケーションレベルのセグメント分け
ワークロード間の通信制御
実践例
従来は同一ネットワークセグメントだった基幹システム群を、より小さな単位に分割し、必要な通信のみを許可する仕組み。これにより、攻撃者が一つのシステムに侵入しても、他のシステムへ簡単に移動できなくなる。
ゼロトラストアーキテクチャの基本コンポーネント

ゼロトラストを実現するためのアーキテクチャには、以下のような基本コンポーネントが含まれます。
アイデンティティとアクセス管理(IAM)
ユーザーやデバイスの認証、認可を一元管理するシステム
主な機能
強力な認証(多要素認証)
シングルサインオン(SSO)
権限管理と最小権限の実施
ライフサイクル管理(アカウント作成から削除まで)
代表的な実装
Azure Active Directory (Azure AD)
Okta Identity Cloud
Ping Identity
ForgeRock Identity Platform
ポリシー決定ポイント(PDP)
アクセス要求を評価し、許可/拒否を決定するコンポーネント
主な機能
動的なアクセスポリシーの評価
リスクベースの決定
継続的な再評価
コンテキスト情報の考慮
代表的な実装
Microsoft Conditional Access
Cisco Duo Beyond
Zscaler Private Access
Palo Alto Networks Prisma Access
エンドポイント保護
デバイスのセキュリティ状態を評価・強化するコンポーネント
主な機能
デバイスの健全性評価
パッチ管理
マルウェア対策
エンドポイントDLP(データ漏洩防止)
代表的な実装
Microsoft Defender for Endpoint
CrowdStrike Falcon
VMware Carbon Black
SentinelOne Singularity Platform
ネットワークセグメンテーション
システムやネットワークを論理的に小さな区画に分離し、アクセス制御を強化するコンポーネント
主な機能
マイクロセグメンテーション:
ネットワークを非常に小さな単位に分割し、きめ細かな通信制御を実現する技術。従来の「営業部ネットワーク」「開発部ネットワーク」といった大きな分け方に比べて、より細かい制御が可能。
東西トラフィック(内部通信)の可視化と制御:
「東西トラフィック」とは、ネットワーク内部での横方向の通信(サーバー間、アプリケーション間の通信など)のこと。従来は外部との通信(南北トラフィック)の監視が中心でしたが、内部の通信も監視・制御することで、侵入者の内部での移動を制限する。
ソフトウェア定義ネットワーキング:
物理的な機器構成に依存せず、ソフトウェアでネットワーク構成や制御を柔軟に行う技術。ネットワーク構成の変更が容易で、セキュリティポリシーの一元管理ができる。
セキュアアクセスサービスエッジ(SASE):
ネットワークセキュリティとWANのサービスをクラウドで統合した新しいモデル。ユーザーやデバイスがどこにいても一貫したセキュリティポリシーを適用できる。
代表的な実装
VMware NSX
Cisco DNA Center
Illumio Core
Guardicore Centra
セキュリティ監視・分析
システム全体の監視と異常検知を行うコンポーネント
主な機能
リアルタイム監視
異常検知
脅威インテリジェンスの統合
インシデント対応の自動化
代表的な実装
Microsoft Sentinel
Splunk Enterprise Security
IBM QRadar
Elastic Security
ゼロトラスト導入の課題と対策

ゼロトラストへの移行は一朝一夕には実現できません。以下のような課題と対策を理解しておきましょう。
組織的な課題
1. 組織文化の変革
課題:「信頼しない」という考え方への抵抗
対策:経営層からの明確なメッセージと、セキュリティ教育の徹底
2. 既存投資との整合性
課題:既存のセキュリティ対策との整合性の確保
対策:段階的な移行計画と既存システムの活用方法の明確化
3. 専門知識の不足
課題:ゼロトラスト実装に必要なスキルセットの確保
対策:外部専門家の活用と内部人材の育成計画
技術的な課題
1. レガシーシステムの統合
課題:ゼロトラスト対応が難しい古いシステムの扱い
対策:封じ込め戦略と段階的な近代化計画
2. 運用複雑性の増加
課題:きめ細かな制御による運用負荷の増大
対策:自動化とオーケストレーションの積極的活用
3. ユーザー体験への影響
課題:セキュリティ強化に伴うユーザー体験の低下
対策:フリクションレス認証(ユーザーの負担が少ない認証方法。例えば顔認証や指紋認証、行動分析による自動認証など)などのUX向上技術の導入
実装のためのベストプラクティス
1. スモールスタート、段階的拡大
特定のアプリケーションやユーザーグループから開始
成功事例を作ってから拡大
「ビッグバン」アプローチを避ける
2. ビジネス目標との整合性確保
セキュリティ強化だけでなく、ビジネス価値を明確に
デジタルトランスフォーメーション計画との連携
ユーザー生産性向上との両立
3. 継続的な評価と改善
ゼロトラスト成熟度の定期的評価
セキュリティメトリクスの設定と測定
フィードバックループの確立
よくある疑問・注意点
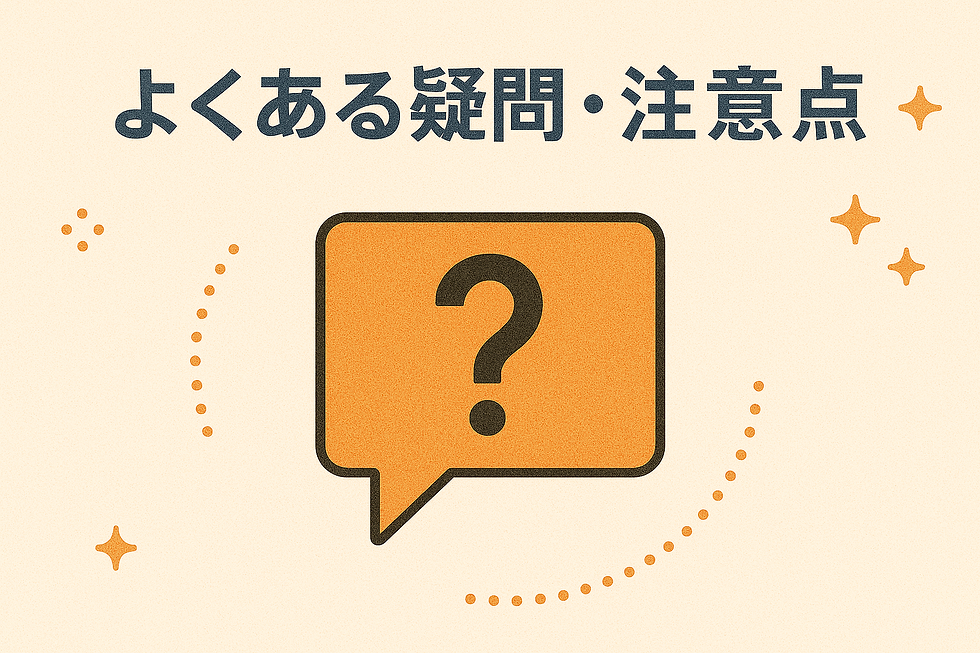
Q1: ゼロトラストは「すべてを疑う」というのは極端すぎないか?
A: 「信頼しない」とは、何も検証せずに信頼しないという意味です。適切な検証をパスしたものは「一時的に信頼する」という考え方です。また、リスクに応じた検証レベルの調整も可能です。すべてを常時最高レベルで疑うわけではなく、状況に応じた適切な検証を行うことがゼロトラストの本質です。
Q2: 既存のインフラを全面的に置き換える必要があるのか?
A: いいえ、ゼロトラストは設計思想であり、既存インフラを活かしながら段階的に実装することが可能です。例えば、まずはアイデンティティ管理の強化から始め、次にエンドポイント保護を改善し、徐々にネットワークセグメンテーションを進めるといった段階的アプローチが現実的です。既存の境界防御を維持しながら、ゼロトラストの要素を取り入れていくハイブリッドアプローチが一般的です。
Q3: ゼロトラスト導入のコストパフォーマンスは?
A: ゼロトラスト導入には初期投資が必要ですが、長期的には以下のようなコスト削減効果があります:
セキュリティインシデントによる損害の減少
コンプライアンス違反のリスク低減
クラウド移行とリモートワークの効率化
VPNなど従来型インフラの最適化
投資対効果を最大化するには、組織のリスク評価に基づいた優先順位付けと段階的実装が重要です。
Q4: ゼロトラストはコンプライアンス要件を満たせるか?
A: ゼロトラストモデルは、多くの規制要件の精神に合致しています。例えば以下のような規制への対応が容易になります:
GDPR(EU一般データ保護規則):EU圏の個人データ保護に関する規則
PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準):カード情報を扱う企業が従うべき基準
HIPAA(米国の医療情報保護法):医療情報の取り扱いに関する規制
特に「最小権限」「データ保護」「アクセス制御」などの要件に対応しやすくなります。ただし、特定の規制への対応には、規制固有の要件を考慮した実装が必要な場合があります。ゼロトラストは多くの場合、コンプライアンス達成の手段となりますが、それ自体がコンプライアンスを保証するわけではありません。
今日からできる!ゼロトラスト移行のための第一歩

ゼロトラストへの移行は長期的な取り組みですが、今日から始められるアクションもあります。
現状評価
組織の現状を以下の観点で評価しましょう
アイデンティティ管理
多要素認証の導入状況は?
特権アカウントの管理は適切か?
SSO(シングルサインオン)は導入済みか?
エンドポイント管理
会社支給/個人デバイスの管理状況は?
エンドポイント保護ソリューションの導入状況は?
デバイスの健全性評価は行われているか?
ネットワーク可視性
内部トラフィックの可視化レベルは?
どの程度セグメンテーションされているか?
クラウドリソースへのアクセス管理は?
データ保護
機密データの分類は行われているか?
データアクセス制御のきめ細かさは?
暗号化の適用状況は?
短期的なアクション
評価結果を踏まえ、以下のような短期的アクションから着手しましょう
多要素認証の導入・強化
特に特権アカウントや重要データへのアクセスから実装
資産の棚卸しと可視化
どのデバイス、アプリケーション、データが存在するか把握
アクセスポリシーの見直し
最小権限の原則に基づき、既存の権限を見直す
セキュリティ意識向上トレーニング
従業員向けにゼロトラストの考え方を説明し、協力を求める
パイロットプロジェクトの実施
特定のアプリケーションや部門でゼロトラストの要素を試験導入
中長期的なロードマップ作成
短期的なアクションと並行して、以下のような中長期的なロードマップを作成しましょう
フェーズ1:基盤強化(3-6ヶ月)
アイデンティティ基盤の強化
エンドポイント管理の改善
資産可視化の拡充
フェーズ2:保護強化(6-12ヶ月)
マイクロセグメンテーションの導入
データ分類と保護の強化
監視・分析能力の向上
フェーズ3:最適化(12ヶ月以降)
ポリシー自動化の拡大
ユーザー体験の最適化
ゼロトラスト成熟度の向上
まとめ:ゼロトラストは旅の始まり

ゼロトラストセキュリティは、単なる技術やプロダクトではなく、現代のデジタル環境に適応するためのセキュリティ哲学です。「何も信頼せず、常に検証する」という原則に基づき、アイデンティティを中心に据え、最小権限の原則を徹底し、継続的な監視と検証を行うことで、より強固なセキュリティ体制を構築できます。
従来の境界型セキュリティからゼロトラストへの移行は、一朝一夕には実現できません。しかし、段階的なアプローチと明確なビジョンを持って取り組むことで、確実に前進することができます。
重要なのは、完璧を求めるのではなく、今日から一歩ずつ前進することです。組織の現状を正確に評価し、リスクに基づいた優先順位付けを行い、段階的に実装していきましょう。
次回の「ゼロトラスト時代のセキュリティ 2: IDaaS導入とアイデンティティ管理」では、ゼロトラストの中核となるアイデンティティ管理について、より詳細に解説します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!


